こんにちは!
今回は、「地震保険ってどこに入るのがいいの?」という疑問に、分かりやすくお答えしていきます。
さらに、いざという時に備えて「絶対にそろえておきたい防災グッズ」もまとめました。
🏠 1. 地震保険って、どこがいいの? おすすめのサイト5選!
実は、地震保険はどこで入っても内容はほぼ同じです。なぜなら、地震保険は政府と保険会社が一緒に運営している仕組みだから。
もっと詳しく説明すると、こういうことになります。
「地震保険は、国がサポートしてくれる安心な保険」
地震保険は、実は少し特別な保険です。
民間の保険会社だけでなくて、国(政府)も一緒に運営している仕組みになっています。
どういうことかというと…
地震で大きな被害が出ると、保険会社だけではすべてのお金を払いきれなくなることもあります。
でも地震保険は、国が一部をカバーしてくれるので、万が一のときも安心して保険金が支払われるようになっているんです。
つまり、国が後ろ盾になってくれている公的な保険なので、倒産の心配もなく、信頼して加入できます。
でも、どの火災保険とセットにするかで、使いやすさや特典が変わるのです!
そこで、おすすめの比較サイトを5つご紹介します👇
おすすめ比較サイト
- 価格.com
保険料や補償内容を簡単に比べられるサイト。いろんな保険会社を比較でき、シミュレーション機能も多彩で大変便利! - my best
地震保険の特約が詳しく書かれていて、初心者にもやさしいです。火災保険の選び方、タイプ別に火災保険を探せたり、戸建て向け火災保険のおすすめ人気ランキングがあり、見やすい! - ウィズマネ
火災保険でネット契約できるところがすぐわかる!火災保険会社・共済19社から調べられるので便利!人気のプランがランキングで紹介されていて、自分に合ったものが探しやすい! - ほけんの窓口
店舗やオンラインで相談しながら決められるので、安心感バツグン! - 火災保険のGift 安い保険会社がすぐ見つかる、 無料で一括見積をしてもらえる!
🔍 2. 地震保険を選ぶときに見ておくポイント3つ
地震保険はどれも似ているようで、チェックすべきポイントがあります。
見ておくポイント
- 火災保険とのセット内容
地震だけじゃなく、火災も一緒に補償されるかをチェック! - 支払われる条件(損害の程度)
「全損」「半損」「一部損」などで、保険金の金額が変わります。 - 契約期間と保険金額
契約期間は長い方がおトクなことも。補償の金額は建物と家財で調整できます。
💡 3. 地震保険って入ったほうがいいの?
もちろんです。入っておくべき理由がちゃんとあります!
加入するメリット
- 国と保険会社が一緒に運営してるから安心!
大きな災害があっても、国の支援で対応できます。 - 支払い条件がハッキリしてる!
損害の程度によって決まってるので、分かりやすいです。 - 住まいの再建や仮住まい費用の助けになる!
被災後すぐの生活費にも役立ちます。
⚠️ 4. 契約前に気をつけたいこと3つ
地震保険に入る前に、次の点はしっかり確認しておきましょう。
注意ポイント
- 補償されないものがある!
自動車や現金、宝石類などは対象外です。 - どれくらい補償されるか確認しよう!
建物の何%まで補償するかを選べるので、バランスよく設定を。 - ちょっとの被害じゃ支払われないことも
「一部損以上」が支払いの条件になるので要注意!
🧰 5. 地震に備えておくべきアイテムはこれ!
「保険に入ってるから安心!」と思いがちですが、いざという時に必要なのは“モノ”です。
ここでは、防災のプロがオススメする備えておきたい必須アイテムを、5つのカテゴリーに分けて紹介します!
✅ 水・食料・燃料系
- 飲料水(1人あたり3リットル×3日分)
- レトルト食品・乾パン・缶詰など
- カセットコンロとガス缶
✅ 情報・照明・通信系
- 手回しラジオ(スマホ充電もできるタイプがおすすめ)
- 懐中電灯+予備の電池
- モバイルバッテリー(容量多めが安心)
✅ 衛生・トイレ・医療系
- 救急セット・常備薬
- 簡易トイレ・ウェットティッシュ
- マスク・アルコール除菌スプレー
✅ 衣類・生活用品系
- 防寒シート(アルミブランケット)
- 軍手・ホイッスル・ガムテープ
- 室内スリッパや替えの靴
✅ 貴重品・個別対応グッズ
- 現金・身分証・保険証のコピー
- 女性:生理用品、防犯ブザー
- 赤ちゃん:紙おむつ、哺乳瓶、母子手帳のコピー
- 高齢者:常備薬や介護用品
✅ 最後にひとこと
- 地震保険は「どの保険会社がいいか」よりも「どんな火災保険とセットにするか」がカギ!
- 比較サイトを活用して、自分にピッタリな保険を見つけましょう。
- そして、保険だけでなく「防災グッズ」もきちんと準備しておくのが、安心の第一歩です。
「万が一の備え」は、今日から始められます!
家族を守るためにも、できることから少しずつ始めてみましょう。
リンク
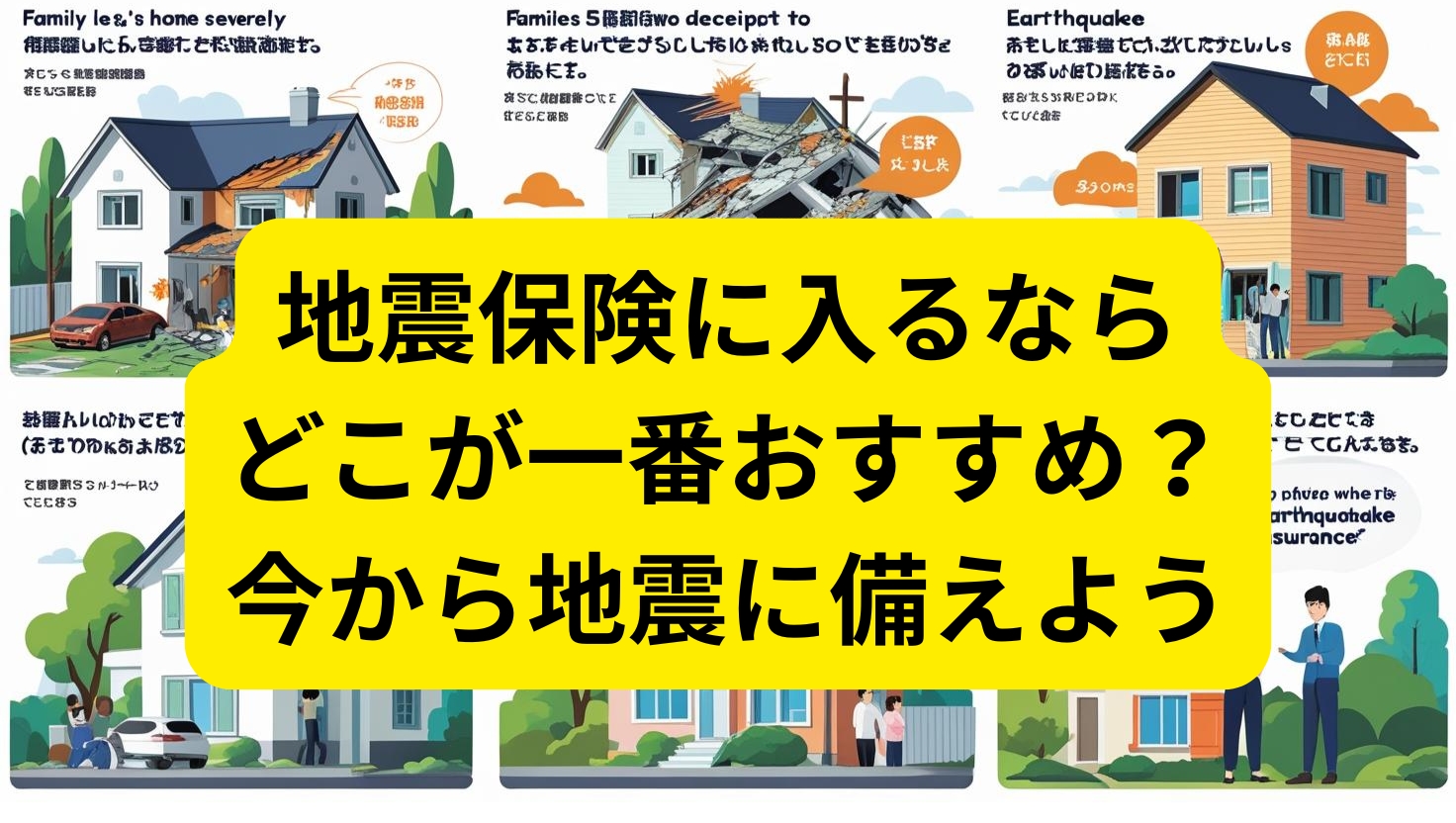
コメント